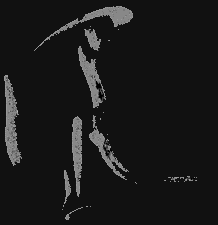木 村 尚 樹
photographic arts
この稿で言う写真美術とは、
写真という媒体を通して表現される芸術の下位概念の一部として位置づけられるものであり、
作者という主体が規定されることで成立する、
「作品」「制作物」といった対外的評価を前提とした
人間の欲求を制度的に可視化したものとしての
「美術」を指す。
すなわち写真美術とは、
社会的承認・評価・流通を前提とした美術体系の内部において、
写真という表現形式が担う一領域である。
「零式(Zero-horizon)」の意味するところは、
芸術の区分けにおいて限界芸術を直接的に継承するものではなく、
限界芸術が指し示した「制度の外縁」という視点を、
さらに生成構造の次元へと押し下げる試みである。
零式は、限界芸術の根源的境界線上、
すなわち「成立しないもの」「制度化されないもの」そのものではなく、
それらが生じる以前の地平――
現象学で言うところの、
いまは見えていないが、必ずそこにあるとされる〈地平〉
に注目する。
ここで零式が据える「零(≒0)」とは、
無限性そのものではなく、
存在と非存在が分岐する直前の閾値としての概念である。
限界芸術の境界として語られてきた「零」は、
「無=0」ではない。
それは、0に限りなく近づきながら、なお僅かに存在するもの、
すなわち、存在が消えゆく際に残る
最小限の生成可能性を意味する。
また零式においてこの「零」は、
モチーフとしてではなく、
零細≒微細な現象として扱われる。
その不確定な成り立ちから、
僅かに無を取り囲むように立ち上がる、
多様で不規則な「蟠り」を内包する。
すなわち、生成過程に伴って現れる非定常な状態としての「ゆらぎ」を、
その内部に含み込む。
したがって「零式写真美術」とは、
零式において定義されたこの生成構造を、
表現対象として扱うのではなく、
それが立ち上がる条件そのものを経験可能にするための設え(システム)である。
それは、
写真を芸術として扱う際に、
作品が美術品として結晶化される以前の生成過程を含んだまま、
制度的形式へと橋渡しするための
概念的枠組みとして据えられる。